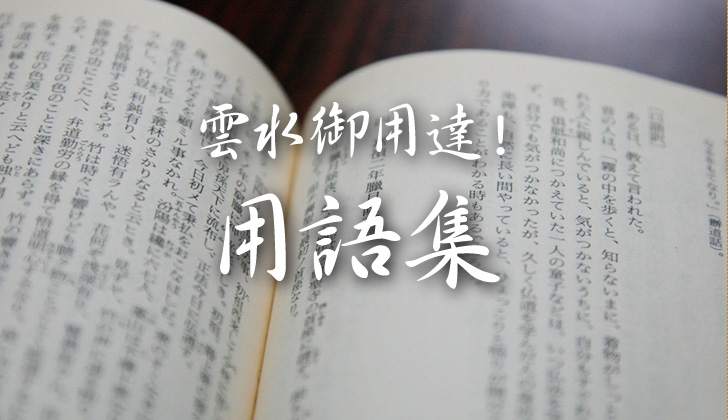簡単にいうと「ごめんなさい」をする儀式。
永平寺では室内看経(しつないかんぎん)といって、朝の法堂でのおつとめの後自寮に戻り、それぞれのご先祖さまに向かってお経を挙げるがその時に唱えるのがこの懺悔文である。
ちなみに「謝る」と「感謝」は同じ漢字が使われている。
お坊さんは清く正しい存在だと想われがちだが、普通の人以上に悪いこともする。
だからこそ永平寺では毎日の「ごめんなさい」を忘れないのである。
【原文】
我昔所造諸悪業(がしゃくしょぞうしょあくごう)
皆由無始貪瞋癡(かいゆうむしとんじんち)
従身口意之所生(じゅうしんくいししょしょう)
一切我今皆懺悔(いっさいがこんかいさんげ)
【和文】
我れ昔より造れる諸(もろもろ)の悪業は、
みな無始の貪・瞋・癡に由りて
身と口と意(こころ)従りの生みものなり
一切、我れ今懺悔したてまつる。
【意訳】
私がしてしまったあらゆる悪い行いは、
すべて始まりのない、欲、怒り、愚かさによって
身体、口、心から生じてしまったものです。
私はすべてを、今、ここで懺悔します。
禅僧のよくなる第一の用心は只管打坐なり
と老師によくよく言って聞かされた。
何も考えないでタダヒタスラ坐禅をすることを只管打坐と言う。
坐禅を始めると禅語録を読んだり、公案や呼吸法、ほっておけばさまざまな思考を巡らせてしまう。道元禅師は坐禅の時は諸縁を放捨し、萬事を休息し、善悪を思わず、是非を関することなかれ、と伝えている。
「ひたすら」という言葉を辞書でひくとこの「只管」という言葉が出てくる。
これは弛緩という意味にも通じる。
でも本当のところはどうなんだろう。
永平寺にいる時によく読んでいた本がある。
人間の受精卵からの発生の過程を詳しく考察している三木茂夫さんの本だ。
夢中で読んでは坐禅をしていた時に「ストレスがたまると内蔵にくる。元々人間は内蔵だ。道元さんはひょっとしてただただ、クダにかえってみる、という自分自身の感覚を込めてこの感じをあてたのではなかろうか」と浮かんできた。
只管打坐。
お寺のお堂の集まりのことを伽藍という。
永平寺では山門、仏殿、法堂、僧堂、庫院、東司、浴司の七つの代表的な修行の場があり七堂伽藍とよんでいる。
作務衣に絡子をつけたスタイルのことをサムラクという。
作務タオルの略。作務をするときに頭にまくタオルのこと。または作務衣で頭にタオルを巻いた状態をさす。
類義語に作務衣に絡子をつけたサムラクもある。
永平寺での修行を終えて娑婆に還っていくことを送行という。
永平寺内にはたくさんの寮舍があるが永平寺の外にも実はなにげに寮舍があったりする。
名古屋別院(愛知)
吉峰寺(福井)
紹隆寺(鹿児島)
の三つがそれである。
外寮舍はお檀家さんがあったり独自のスケジュールで動いていたりするので年配の雲水や怪我をしている雲水がいくこともある。
問題を起こして外寮舍に転役する場合「外寮舍にとばされる」などと言うこともある。
しかし独自の雰囲気が魅力的で自分は安居中紹隆寺にいってみたかったものだ。